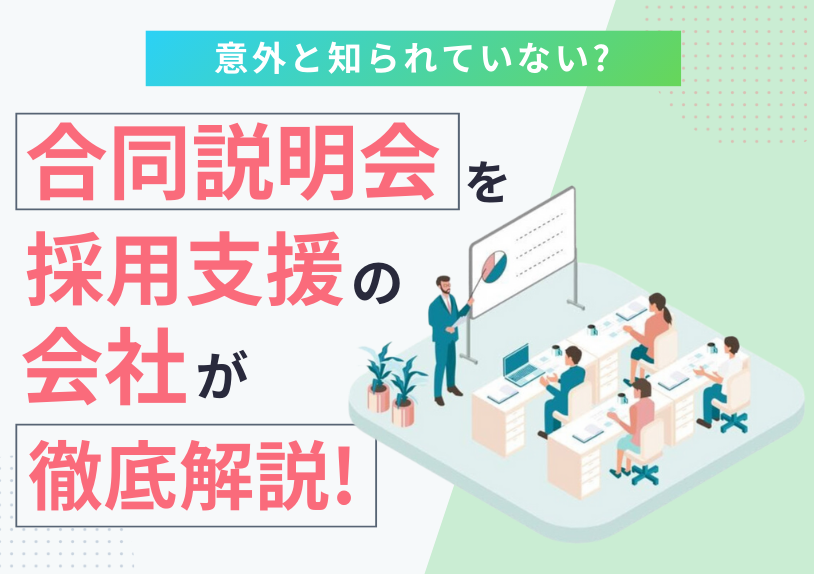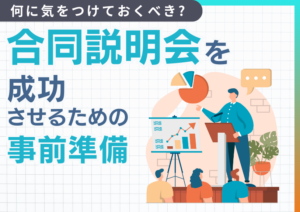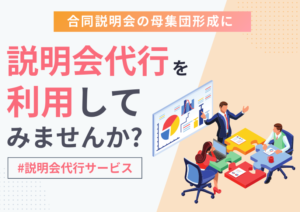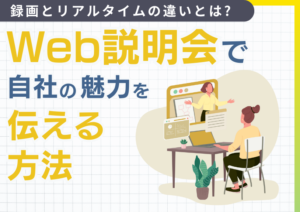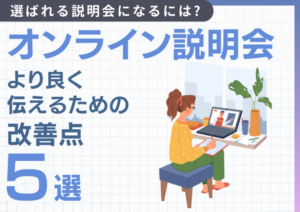意外と知らない合同説明会について採用支援の会社が徹底解説
採用活動の中でも大きなイベントとして挙げられるのが合同説明会となります。
この時期が近づくと人事部も準備に忙しくなり、いよいよ採用活動が本格的になってきたと感じるのではないでしょうか。
合同説明会の後には単独説明会や面接を始めとする選考過程が続くことになりますので、ここでうまく流れを作りたいところだと思います。
そこで、今回はこの合同説明会を成功させるために知っておくべき基本について再確認を兼ねて採用支援の会社が徹底解説いたします。

合同説明会に特化したオウンドメディアを運用中!

プロ人事が運営するオウンドメディア「合同説明会トレンド」にて、
合同説明会に関する情報やノウハウを日々発信中です。
合同説明会に特化したこちらもぜひご覧ください!
※外部サイトに遷移します。
合同説明会の役割と目的とは?
合同説明会の役割や目的について、しっかりと理解しているという方は意外と少ないのではないでしょうか。
合同説明会を成功させる上で、様々な工夫があるのですが、まず合同説明会で目指すべきものがなにかを明らかにしなければ改善点も見えてきません。
ここでは、単独説明会と比較しながら、なぜ合同説明会を行うのか、合同説明会にはどんな種類があるのかについて解説したいと思います。
合同説明会と単独説明会の違い
前提として、合同説明会は新卒を対象として行われることが多いです。
最近は中途採用向けの合同説明会も開催されるようになりましたが、その場合は求職者側にある程度希望の転職先が決まっていることも多いため、面談や面接など、求人の選考過程に進むことになります。
また、合同説明会と単独説明会の2つに分けられます。それぞれの違いは以下の通りです。
- 合同説明会
-
外部企業が主催となって、複数の企業が参加しそれぞれのブースで企業説明を実施。
複数の企業の説明会を聞くことが可能である。 - 単独説明会
-
単体で企業が実施する説明会。
原則参加者はその企業にエントリーを決めている者が参加する。
すなわち、複数の企業と合同で開催するか、自社単体だけで開催するのかが違いとなります。
また、合同説明会・単独説明会ともに、共通する目的として以下の2点が挙げられます。
- 母集団の形成…求人の応募につなげるために必要な集団(母集団)を作る
- 就活生の意向醸成…企業に魅力を感じてもらい、求人に応募してもらうようアピールする
合同説明会が持つ役割
合同説明会と単独説明会では、先に合同説明会が先行して開催されることが多い傾向です。
とはいえ、それぞれに課せられた役割が異なります。次の項目でそれぞれ解説していきましょう。
- ①合同説明会の役割
-
合同説明会は、主に就職活動が解禁された3月〜5月にかけて開催されます。
この時期の学生は、志望業界も決まっておらず、情報収集のために合同説明会に参加している者も多くを占めているため、まずは企業について業界や特徴を知ってもらう必要があります。
採用活動の初期段階で行われるイベントであることから、合同説明会は母集団の形成を主な目的とし、また後続する単独説明会への誘致の役割を兼ねています。
- ②単独説明会の役割
-
自社だけで行われる説明会ですので、就活生もその企業に一定以上の興味がある状態で参加しています。
参加者に求人のエントリーをしてもらうために、より自社のことを知ってもらうために開催をすることなります。そのため、合同説明会よりもより就活生の入社意向への醸成がメインとなってきます。企業によっては、選考の役割を兼ねている場合もあります。
このように、説明会の共通目的はあるものの、合同説明会と単独説明会のそれぞれで重視する目的が変わってきます。
合同説明会の種類
合同説明会の種類に関しては、開催規模によってさらに細かく分けられます。
分類は以下のとおりです。
- 大型合同説明会
-
100社程度の企業が参加する合同説明会
- 小型合同説明会
-
5社程度の企業が参加する合同説明会
- WEB合同説明会
-
WEB上で行う合同説明会
上記で紹介した開催の形式以外に「同業界」「文系・理系(学部別)」「地域別」であったりと、企業の特徴や性質毎に共通する企業が複数参加するものもあります。
特に後者で挙げたようなものは、就活生もある程度就職したいと考える企業の条件を考えている者など参加する就活生の就職に対する意識のレベルが変わってきますので、それに合わせてブースの運営やプレゼンの構成等も変える必要があります。
合同説明会ですべきこととノウハウをお伝えします!
合同説明会と単独説明会の違いや目的について確認したところで、次に合同説明会では何をやらなければならないのか、どう行っていくのが良いのかについて解説したいと思います。
① 運営に必要な準備

簡単に合同説明会の実施にあたってやるべきことについて紹介しましたが、次に実施にあたって合同説明会の実施に関するノウハウについて、合同説明会の目的に沿ったものを解説いたします。
自社がどのような人材を採用したいと考えているのか、ターゲットを設定します。
ターゲットの設定時は漠然と考えるのでなく、出身学部をはじめ、授業・サークルの取り組み方や将来のキャリアプランなど、詳しくペルソナを設定しておきます。
あらかじめターゲット(ペルソナ)を明確にしておくのは、合同説明会実施計画の進行をスムーズに進めることにつなげられるからです。
最初の段階でどのような学生に応募してほしいか設定しておけば、プレゼンの内容やプレゼンターをどのような人にお願いするべきか、おのずと後の活動指針が見えてきます。
合同説明会時点では、呼び込んだ就活生がターゲットにあたるかの判断をすることはできませんが、ここのスタート地点からぶれてしまうと、その後の工程でブレが生じてしまい結局欲しい人材が採用できなかったということもあります。
合同説明会にかぎらず、採用活動全体のスタートとして必要なので、しっかりとターゲット(ペルソナ)を練っていきましょう。
ターゲット(ペルソナ)を設定したら、自社の魅力とターゲットに響く伝え方を明確にしておきます。
この時、必ず就活生の視点に立ってみるように心がけましょう。
合同説明会は就活生が情報収集をする場でもあります。
就活生の視点を落として、自社が伝えたいことばかり一方的に聞かせるだけでは、就活生の心に響くことはありません。
②で考えたアピール内容を元に、プレゼンの構成や内容、誰にプレゼンターをお願いするのかを決めていきます。
プレゼンターの選出については、会社の役職毎に就活生に与える影響も変わってきますので、どのような人材を採用したいのかや伝えたい内容に合わせて選定すると良いでしょう。
決まったら早めにスケジュール調整をすることも忘れないようにしておきましょう。
合同説明会の運営は、プレゼンの実施だけでなく、参加している就活生の呼び込みが必要となってきます。ある程度知名度が高くないと自主的に就活生がブースに立ち寄ってくるということが難しいため、積極的に呼びこんでいく必要があります。
そのためプレゼンター以外にも呼び込みをする人員の手配が必要となってきます。人員の数としては、ブースに入れる人数に制限もありますが、昼休憩時などの交代要員を作れる余裕があると良いです。
昼休憩中はブースの運営も停止することも考えられますが、集客率を上げるならば昼休憩をずらしてとれるようにすることで停止させることなく運営できるようにすることをオススメしております。
就活生に配布する資料やプレゼンに必要となるプロジェクターやスクリーンはもちろんのこと、ブースを装飾するために使用するポスターやパネル、椅子のカバーについても準備しておきましょう。
ブースの大きさ・広さなどは当日にならなければ分からないため、多めに用意しておくようにし、使用するポスター・パネルについて何を全面にアピールしたいのかをもとに優先順位を決めておくと当日の準備がスムーズに行うことができます。
プレゼンの実施時間・質疑応答の時間などの設定や休憩を取りに行く時間を大まかにでも決めておくことで、当日スムーズに運営することができます。
もちろん絶対的に予定通りに行くとはいかないかもしれませんが、特に交代に関して手間取ってしまいブースの運営が滞ってしまうようなことがあると、集客率が下がってしまうことになるため注意が必要となってきます。
② 合同説明会を成功させるためのノウハウ
合同説明会の主な目的の1つは「母集団形成」です。
母集団の形成をする上で、まず重要となるのは合同説明会に参加する就活生の数=集客数を増やすことになります。
ここでは、集客数を上げるポイントについて3つご紹介します。

①就活生の呼び込みを重視する
上述にもあるように、就活生の呼び込みをしなければ参加してくれる就活生の数は伸びません。
というのも、合同説明会に来ている就活生は、希望する業界も決まっておらず、業界・企業研究のために参加している者も多く、とりあえず知っている企業のブースに行って話を聞いてみるという行動をとりがちです。このような就活生は知名度の大きい企業やBtoC系の企業のように何かしらの形で目にする機会があったものしか知らないということもあり、なかなか知名度が低い企業やBtoC系の企業は待っているだけでは、就活生が来てくれません。
そのため、企業から積極的に就活生に呼び込みをしていく必要があるのです。
②プレゼンの時間は15分程度がおすすめ
合同説明会のプレゼンの実施時間について30分ほどかけるという企業も多いのですが、集客率を上げるという点からすると適切な実施時間とはいえません。プロ人事としてはプレゼンの実施時間を15分程度をオススメしています。
プレゼンの時間の短縮をオススメしている理由として、まず単純な話ではありますがプレゼンを実施する回数を増やすことでプレゼンに参加する就活生の数も増やすことができます。
会社の魅力を知ってもらうのであれば、しっかりと時間をかけてアピールした方が良いのではないかと思われるかもしれませんが、そもそも時間をかけれ話をしたからといって就活生にわかってもらえるという認識が誤りなのです。というのも、この認識は、就活生が最後まで話を聞いているということが前提となってくるのですが、実際のところ話のすべてを聞いているということは稀であり、最初から興味がある者でない限り難しいものになってきます。また、就活生は複数の企業説明も聞きに行くことになりますので、全てを覚えておくということはナンセンスな話と言えます。
ですので、長時間かけたとしても、ほとんどが無駄になってしまう可能性が高くなります。
むしろ、合同説明会では伝えたいことを絞って実施時間を短くして、集客率を上げる方が効率的であると言えます。
合同説明会は単独説明会への誘致の役割も兼ねているため、あえて合同説明会では伝えたいことすべてを説明するのではなく、むしろもったいぶるくらいにして就活生の気を引いて単独説明会へ誘導するという構成にするのもおすすめです。
③プレゼンの構成を工夫する
プレゼンの実施時間に関連してプレゼンの構成も工夫することで集客率アップを図ることができます。
具体的には、プレゼンの冒頭部分に時間をかけて本編部分を短く構成するというものです。
なぜ、冒頭部分を長くするのか、本編の部分の方が重要なのだからそちらを長くした方がよいのではないかと思われるかもしれません。
たしかに、魅力をアピールするならば本編にかける時間を長くするのが通常ですし、この考え自体が誤っているというものでもありません。
しかし、本編を長くする構成だと集客率を上げるという点からネックになることがあります。というのも合同説明会では、各ブースで説明会の実施時間が異なっているため、就活生の行動にバラツキがあります。
そのため、説明会が開始されてから通りがかる就活生に呼びかけをした場合、就活生からすると本編部分を途中から聞くなら、次回の説明会に参加すると考える者も少なくありません。後回しにして、そのまま戻って来ないということも往々にしてあり、せっかく呼び込んだのに逃すのは勿体ないといえます。
そこで、冒頭部分を長くすることで途中からでも参加しやすいようにプレゼンを構成するのをオススメしております。
プロ人事の説明会代行サービスを利用してみませんか?
この記事では集客率を上げることで母集団の形成目的を達成するということを前提にノウハウをいくつか紹介しました。これ以外にも細々としたノウハウはありますが、意外と見落としていた観点や発想などもあったかと思います。
このように、合同説明会の実施について見直すことで初めて気づく改善点もあったりするのですが、なかなか自社だけでは気づきにくいものでもあります。
また、ここまでやるにはなかなかマンパワーも足りず、難しいという企業様も多いかと思います。そのような企業様にオススメしているのが、プロ人事の採用代行サービスとなります。
採用支援の会社であるプロ人事では、様々な採用業務の代行を行っておりますが、ここでは、合同説明会の実施に関するサービスとして【説明会資料作成サービス】と【説明会代行サービス】の2つをご紹介いたします。
①説明会資料作成サービス
説明会で使用する資料の作成の代行を承ります。
当サービスでは採用コンサルティングとデザイナーが連携して資料の作成にあたりますので、視覚的なデザインはもちろんこと、内容に関してもその後の選考過程を意識しつつ、企業の魅力のアピールや応募にあたっての不安ぼ解消ができる資料作りを行います。
また、自社だけでは気づくことができない改善点や他社との比較も第三者の目を入れることで、内製で行う以上のクオリティの改善を致します。
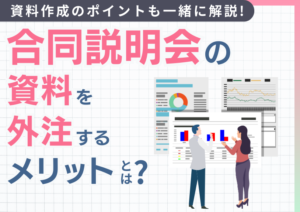
②説明会代行サービス
合同説明会のブース運営の代行を承ります。
こちらのプランは①応援プランと②運営おまかせプランの2つがございますので、ニーズに合わせてご利用ください。
- ①応援プラン
-
人事の方に現場にお越しいただいた上で、プロ人事が追加人員としてブース運営をサポートいたします。
人材の育成の必要がなく、即戦力として起用することがメリットです。
人材育成にかかるコストが削減できるのみならず、プロ人事の有するノウハウを元に呼び込みを行いますので、人事部の手を煩わせることなく集客率を上げることが可能になります - ②おまかせプラン
-
ブース運営を丸ごとプロ人事にまかせるプランです。
人事部が説明会業務以外のコアな業務に集中することが可能になります。
例えば、浮いたリソースを面接業務に回して面接の枠を増やすことで、合同説明会で増えた学生を逃すといった事態を防止することができます。
他にも、説明会でのプレゼンについてのアドバイスも致しますので、プロのノウハウを利用することができるというメリットもございます。
プロ人事の説明会代行サービスでは、安心してご利用していただくために一定以上の人数を集めることができない場合には、頂いた代金の一部を返金する集客保証プランもご用意しております。
サービスの導入やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

合同説明会の運用代行、研修はプロ人事へ!
サービスの導入、ご相談はメールフォームからご相談ください!
2営業日以内に担当者よりご連絡させて頂きます。
\ 期間限定・今なら無料の初回コンサルティング付き!/
無料の初回コンサルティングは予告なく終了する場合がございます。

まとめ
今回は合同説明会の基本的な部分を中心に解説をしてまいりました。
採用活動のなかでも大きなイベントであり、この後に続く採用過程の大きな足がかりとなるからこそ、躓きたくない工程となります。合同説明会を実りあるものにするために様々な準備を行われなければならず、開催までの準備期間はてんやわんやすることになると思います。
人事部は他の部署と比較しても部員数が足りず、当日の運営も他部署に応援を頼まなければ難しいということも多いかと思います。そのような企業様にオススメしているのが、プロ人事の【説明会資料作成サービス】や【説明会代行サービス】となります。
これらのサービスについて興味のある方や利用を検討している方はぜひお気軽にお問い合わせください。