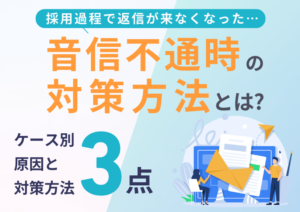適性検査についてのデメリットや事例を解説!
適性検査は、新卒採用や中途採用の両方で使われている手法になっています。
この手法は多くの企業に広く用いられており、近年ではAIの技術を用いて適性検査の精度を上げていくような取り組みもあります。
機械学習の技術などによって適性検査精度が上がっていることなどから、更なる活用が叫ばれている一方で、現場との対立が起きているのも事実となっています。
このような適性検査のデメリットは中々表面化しない上、上層部は現場の一意見として流してしまいがちでもあります。
また適性検査の業者もそのようなマイナス点についてはあまり語りたがりません。
そこでこの記事では、我々プロ人事が中々表には出てこない、採用で用いる適性検査のデメリットをご紹介していきます。
ちなみに何故我々がコンサルタントとして適性検査のデメリットを語れるのかというと、我々は適性検査の導入のお手伝いをしているものの、適性検査で収益をあげようとはしていないからです。
実際の採用の支援をさせていただくことが当社の業務ですので、採用に関わるものについてはフェアに扱ってポジティブな面とネガティブな面の両方を丁寧に説明してきたいと思っています。
この記事では、適性検査のネガティブな面にフォーカスして伝えていくため、結果として適性検査を導入すべきではないと思われる方もいるかと思います。しかしそれが言いたいのではなく、使う際には注意も必要であるということが我々が本当に伝えたいことになります。
良いコンサルタントは、物事の良い点と悪い点をありのままにクライアントに伝えた上で、選択してもらえるものでなければなりません。
適性検査の結果に関しては、上層部としてはフェアに感じるものの、現場の人事としては行き過ぎたスクリーニングとしてむしろ足を引っ張られるように感じることも実際には少なくありません。
そうではなく、育成の部分でもう少しリスクテイクしていく観点も忘れてはならないという意味で、今回の記事を読んでいただければと思います。
\ お気軽にお問合せください!/
1:適性検査のデメリットとは
早速ですが適性検査のデメリットを解説していきます。
適性検査とは、採用で用いられる試験のようなものでそれを応募者に受けさせることで自社にマッチしているかどうかを判定する手法です。
従来は心理学の観点から性格診断が行われていました。
しかし近年の特徴としては、自社の社員にも同じものを受けさせて自社の社員とマッチするかを判断したり、自社の中で活躍している人材と近い属性を示すかどうかでジャッジしていくようになってきました。
更にはその中で、機械学習の技術を用いて自社へのマッチ度をより深く判断するのが近年のトレンドです。
これだけ見ると適性検査はクオリティが高いように思われますが、最先端のものを使っていても担当者には不満があるケースも多々あります。更には、適性検査によって採用のパフォーマンスが落ちてしまっていることも少なくありません。
今回はその背景や、何故そのようなことが発生しているのかを交えながら、適性検査のデメリットを解説していきましょう。
デメリット1:採用したい人材と適性検査のギャップ
そもそも大前提の適性検査の機能に関して、採用したいと思えるような人材と適性検査の結果との間にギャップが発生することがあります。
適性検査側はこのようなことをなくそうと日々努力を続けていますが、実際にこの問題は発生してしまいます。
頻度は適性検査の品質によりますが、適性検査で弾かれてしまっても実際に会って話せば良い印象を受けることも少なくありません。
現場では採用したいと思っていても適性検査で弾かれてしまうケースも多くあり、現場に合っている人材にも関わらず落としてしまうことになってしまいます。
デメリット2:採用担当者の抵抗感
これに関しては、デメリット1とも関わることです。現場担当者が採用したいと思っているにも関わらず、適性検査で落とされてしまうようなことが続いてしまうと、どうしても採用担当としては適性検査に対してネガティブな気持ちを持ってしまいます。
そうなってしまうと、適性検査をいかに通過させるかという本末転倒な思考に陥ってしまうのです。
人気企業で人数を絞らないといけない場合、精度が完全でなくてもスリーニングしてくれるのはいいかもしれません。
しかし、人気度がそこまで高くない場合、どうしても採用担当にも採用の目標がありますので、採用担当者が応募者に対して受からせようとして過度に対策などを教えてしまうことがあります。
軽微な例では適性検査を受ける心構えなどを教えるだけでなく「前向きな気持ちで受けましょう」など、それとなくアドバイスを与えるものもあります。
また、適性検査の存在意義が問われるような「こんな質問にはこう答えましょう」など、行き過ぎた助言を与えたり、適性検査でNGになった場合に再検査を繰り返し、良い結果が出るまで受けさせるなんてケースもあります。
デメリット3:採用への負担の増加
2020年にパンデミックが発生して以降、多くの業種の採用の倍率が下がりました。
一方でエンジニアなどの人気職種の難易度は高いままですし、理系学生が減少している中で今後も理系採用はかなり難しくなっていくと予想されています。
適性検査は自社に合った人材を採用するという最もらしい名目で行われますが、今後採用の難易度が上がってく一方でターゲットを更に狭めていくアプローチは採用の首を絞めることになってしまいます。
経営側からすれば、自社に合った人材を採用したいのは当たり前です。しかしながら、外部環境の変化を考えた際に採用を極端に狭めてしまうようなアプローチが果たして正解なのかどうかは、考えていくべきでしょう。
適性検査によるスクリーニングがあまりにも行き過ぎてしまえば、採用担当者は抵抗を感じることになります。
この抵抗感は言葉を選ばずに言えば、採用担当者のストレスとも言えます。
これらが原因となり、採用はどんどん難しくなっていき、採用担当者の負担が増えています。
採用担当者が自分の目で見て、この人材は自社に合わないなと感じるのはまだ納得できますが、ツールに足を引っ張られるのは違う、という感覚を持っている採用担当者は多いでしょう。
デメリット4:そもそも性格検査による人材の見極めには限界がある
性格検査などをもとに自社にマッチした人材を採用するのは言葉だけ見れば論理的でしょう。
自社に会う人材と合わない人材がいるから見極めないといけない、というのは納得感があります。しかし、異なる職種であればわかりますが、同業他社であれば性格での見極めには限界があるのではないでしょうか。
例えばエンジニアを採用していく際に、エンジニアに向いているかどうかの診断が出るのであれば、エンジニアに向いている人を採用したいのは当然です。それは競合他社も同じように思うでしょう。
同じ適性検査であれば当然同じ結果になりますし、同じエンジニアであれば基本的に同じ業務になりますので、他社が合わない人材は自社も合わないと言えます。
そのように考えた時に、自社にだけ合う人材というものを追求するのでは限界が生まれてしまうでしょう。
またエンジニアでは、会社は違えど業務はほとんど同じような場合があります。クライアント企業に常駐するような職種では、そもそも会社に合う合わないといった概念が存在しません。
その意味では、適性検査で自社に合う合わないというのには限界があるのです。
2:適性検査によってデメリットが生じた事例
次に適性検査を行ったことにより、デメリットが生じてしまった事例をご紹介します。
事例1:採用担当者による適性検査の形骸化
問題としてかなり大きかったのが適性検査の形骸化です。
上層部としてはお金も時間もかけて導入しているので本末転倒ですが、採用担当者としては採用目標もあるため、いかに適性検査をクリアしていくかといった気持ちが働いてしまうことがあります。
この攻略法は会社によってまちまちでしょう。
適性検査の時期を後ろ倒しにして志望度が高い学生の通過率を挙げるためにレクチャーする企業もあれば、答え方のマニュアルを作って配る企業もあります。
実際にやっていることは適性検査の意義を損なうことですが、我々としてはこの現場の不正を見抜こうとすることは本質的ではないと思います。
不正自体は通過率の高さなどから判断することができますが、あまりそんなことをしても意味がありません。
その意味では適性検査の導入から会社としてしっかり検討し切ることも必要ですし、採用担当者の理解をしっかりと得ることが必要です。
事例2:何度も受けさせる採用担当者の登場
適性検査は「1回幾ら」のような形式が多いですが、学生側の通信環境などで何度も受けさせるようなことも可能になっています。
あまりにも学生の結果が悪くて優秀な学生が落ちてしまうようであれば、再度受けさせるようなケースがあるでしょう。
受かるまで適性検査を受けさせるようなことになってしまうと、適性検査を行う意味が失われてしまいますし、学生側の不信感にもつながってしまいます。
その不信感によって学生が辞退してしまうと、そもそも適性検査なんてやらなければよかったと思ってしまうことになりかねません。
事例3:採用担当と育成担当の衝突
2-1、2-2では矛先が適性検査のみに向いていますが、それ以上に問題が拡大してしまうこともあります。
問題が適性検査だけであれば、採用担当に対するマネジメントがしっかりしていれば組織に与える影響は大きくありません。
しかしこの事例では、問題が表面化し組織間の対立にまで及んでしまっているのです。
その対立とは、採用の目標がある採用担当者と育成側の間の対立です。
育成側としては、自社に合った人材が欲しいため採用を厳選させようと思います。
しかし、厳選させるのは採用をより難しくすることでもあり、採用側は「育てやすい人材ばっかり育てようとするなよ。育てづらい人材も育てるのが仕事だろ」というような気持ちになってしまいます。
育成と採用は同じ人事部ですが、利害関係として対立が生まれてしまうのです。
適性検査で採用要件を絞りすぎてしまうと、ギャップが大きくなり問題になってしまいます。
また、育成担当者と適性検査は利害が一致しています。
というのも適性検査のスクリーニングが進むほど、適性検査の意義が生まれ、育成担当者も育てやすい人材が集まりやすくなります。
そのため、適性検査は採用担当者の意向に反して重要視されてしまいがちです。
ただ採用が難しくなっていく中で、全体の最適化を考えた時にネガティブなメカニズムになってしまっているのです。
まとめ-ではどうすべきか。プロの採用コンサルタントの答え
ここでは、適性検査のネガティブな点を解説してきました。
ネット上にも、このように適性検査のネガティブな点をまとめている記事は殆どありません。
また今回は適性検査のネガティブな点を纏めてきましたが、冒頭で述べた通り、我々は適性検査の導入自体に反対しているのではありません。
一方で、採用担当を交えずにトップダウンで導入してしまうのはよくありません。
採用と育成で今後難しくなっていくのは採用の方でしょう。特に、採用難易度の高い業種や職種では、採用の足を引っ張るようなものはやるべきではないといえます。
適性検査は、今後AIなどの発達でクオリティが上がっていくと予想されています。その中で適正検査のベストな活用法は、適性検査はそのまま行う一方で適性検査に最終的なジャッジの権限を与えないことです。
あくまでジャッジは採用担当者や面接官で行いましょう。採用の邪魔をするものではなく採用の助けになる資料にすることが重要です。
適性検査の結果を踏まえて、こういう人材にはこういうアプローチをすればいいと情報をうまく活用していきましょう。
今回の件を踏まえ、適性検査に客観的なジャッジをしてほしいなど採用に関するご相談などあればお気軽に弊社までお問い合わせください。