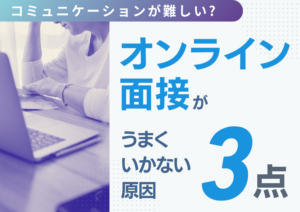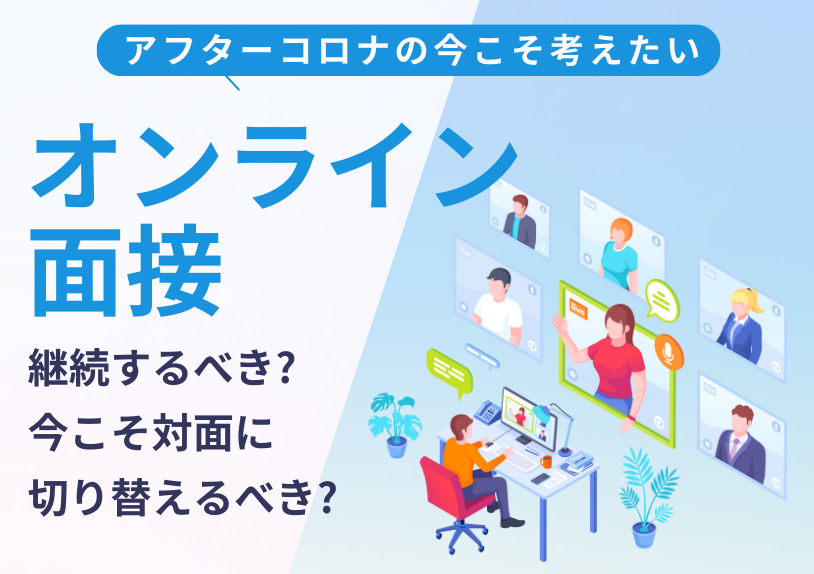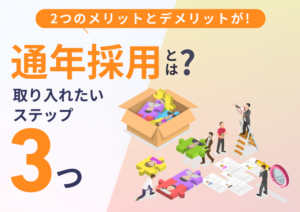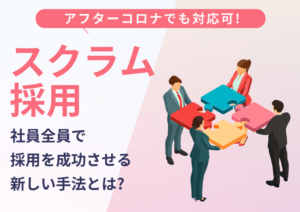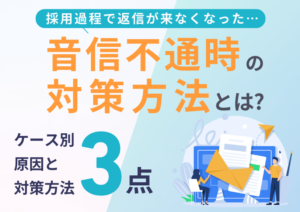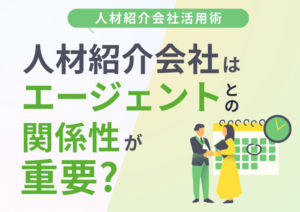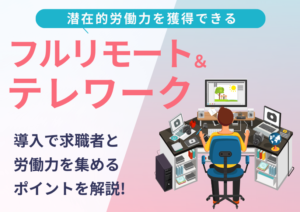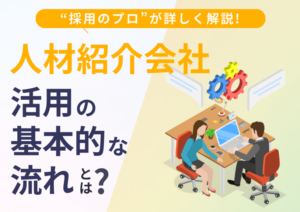2020年の新型コロナウイルスの流行から、採用現場も「新しい生活様式」を取り入れた手法が多々生まれました。
2023年5月8日をもって新型コロナは5類に移行しましたが、「アフターコロナ」という言葉が現実味を帯びてきた現在、改めて変化した制度や体制を存続させるべきかお悩みの企業も多いのではないでしょうか?
この記事では、アフターコロナとなった場合どうするべきか解説していきます。
コロナ渦で生まれた「新しい生活様式」
まず、「新しい生活様式」について改めておさらいしましょう。
「新しい生活様式」は新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言を踏まえて厚生労働省が感染拡大防止のために公表した行動指針です。
具体的に次の行動のように変わりました。

- 身体的距離の確保
「ソーシャルディスタンス」や「3密」という言葉とともに、人との間隔をできるだけ2m(最低でも1m)離すようにするとして、さまざまな場所で人との間隔をあけられるように対策が取られました。
また、緊急事態の発令や「不要普及の外出」を控えて、可能な限り自宅に留まる「ステイホーム」も推奨されました。 - マスク着用
飛沫を防ぐため、外出の際はできるだけマスクを着用することが勧められました。
熱中症を防ぐため気温が高い時は外しても差し支えないという判断があったものの、その際はソーシャルディスタンスを保つようにします。
食事中においても、原則「黙食」とし、やむを得ず会話する際は再度マスクの着用するようアナウンスがありました。 - 手洗い・うがいの徹底
自宅に帰ったら30秒かけて水と石鹸で手洗いを行い、うがいをすることが感染の防止につながります。
また、可能な限りすぐに着替えてシャワーを浴びることで、身体に付着したウイルスを落とすということも提唱されるようになりました。
企業・採用現場で導入された新型コロナウイルスへの対策
では、企業・採用現場ではどのような感染対策がされたのでしょうか。

- テレワーク(フルリモート)の推進
ソーシャルディスタンスを保つために、自宅でも仕事ができるテレワーク(フルリモート)が推進されるようになりました。
これにより勤務形態が変わった方も多いのではないでしょうか。 - 時差出勤の導入
通勤ラッシュは3密を作り出すため、可能な限り出勤の時間帯をずらす対策がとられるようになりました。 - オンライン面接の対応
従来の対面面接では面接官と受験者の会話だけでなく、自宅から会場への移動でも感染のリスクが上がります。
そのため、自宅から面接が受けられる「オンライン面接」が急速に普及しました。
この記事では「オンライン面接」の継続にフォーカスを当てて、詳しく解説していきます!
アフターコロナでは「オンライン面接」を存続させるべきか?
新型コロナウイルスへの対応として急遽「オンライン面接」をはじめとした「新しい生活様式」を導入した企業がほとんどでしょう。
そして、オンライン面接を実際に導入したことで、今までは気付かなかったメリット・デメリットを感じるということもあるのではないでしょうか。
そこで、オンライン面接のメリットやデメリットについて一緒に見ていきましょう。
オンライン面接のメリット
メリット①:遠方の応募者の負担が緩和できる
これまで対面での面接では交通費や宿泊費などの事情から就活生の行動範囲が限られてしまうこともあり、面接を受けたくても面接地が遠く断念せざるを得ないという就活生が特に地方部で多くみられていました。
この点、オンライン面接は面接地との距離は関係なく自宅で受けることが可能となったため就活生にとって選択の幅が増えたと言えます。
そして、これは就活生にとってメリットというだけでなく企業にとってにメリットにつながってきます。
応募者の数が増えるということは、企業にとっての対象となる母集団が増えた可能性が高くなるということでもあります。
メリット②:日程調整が柔軟にできる
対面で行う場合には、会議室などの面接会場を確保しなければならず、会場の確保との関係から面接日程を思うようにとることができないケースもあるでしょう。
特に新卒採用で忙しくなる3月は世間一般でも期末になっており、会議室の奪い合いという事象が多くの企業で起こりえていました。
この点、オンライン面接であれば会場を確保する必要はありません。
また、会場の確保が不要となる他に、面接官は通信機器とネット環境があれば面接をすることが可能となるので、場所を問わず、業務の合間や出張先などのスキマ時間を使って面接を実施することが可能となります。
このように、面接会場が不要となり、面接官の空いた時間をうまく活用することで面接日程の柔軟性を上げることが可能となるのです。
就活生は複数の企業の面接を同時に行っていますので、面接を受けたくとも日程調整がうまくいかずに面接を受けることができず断念するという方もいます。
これまで面接日程を確保することができなかったために欲しい人材を知らず知らずのうちに逃してしまっていたということもオンライン面接を使うことで防ぐことが可能となるのです。
オンライン面接のデメリット
デメリット①:表情や声から読み取れる情報が少ない。

対面とは異なりどうしても画面越しにやり取りをすることになってしまうため、対面であれば表情や声のトーンなどから細かい機微を感じることができていたことがオンライン面接だとできなくなってしまうという事態が生じやすくなります。
そのため、面接官にとっては採用の可否の要因となる情報が対面よりも少なくなってしまうというデメリットが上げられます。
またネットを介して行われるため、会話にラグ等が生じてしまいテンポが合わず面接官や就活生にとってコミュニケーションがスムーズに行えず双方にとってストレスを感じるということもあると言えます。
そして、結果的には「入社して欲しい人材」へのアプローチや意向醸成が上手くいかないケースもあり、結果的に入社して欲しい人材が他社に奪われてしまうという事象が生じてしまいやすいのもオンライン面接のデメリットとなっています。
デメリット②:通信機器やネット回線のトラブルで、面接が中断してしまう

また面接を実施している際中に使用している通信機器やネット回線のトラブルによって面接がスムーズに行われないことや、最悪の場合には中断しなければならないといったこともあります。
対面であれば、面接を開始してしまえば中断等のトラブルという不安もなく終わっていたことがオンライン面接だと上記のリスクが生じてしまうということがあるといえます。
デメリット③:面接の種類や内容が制限される。
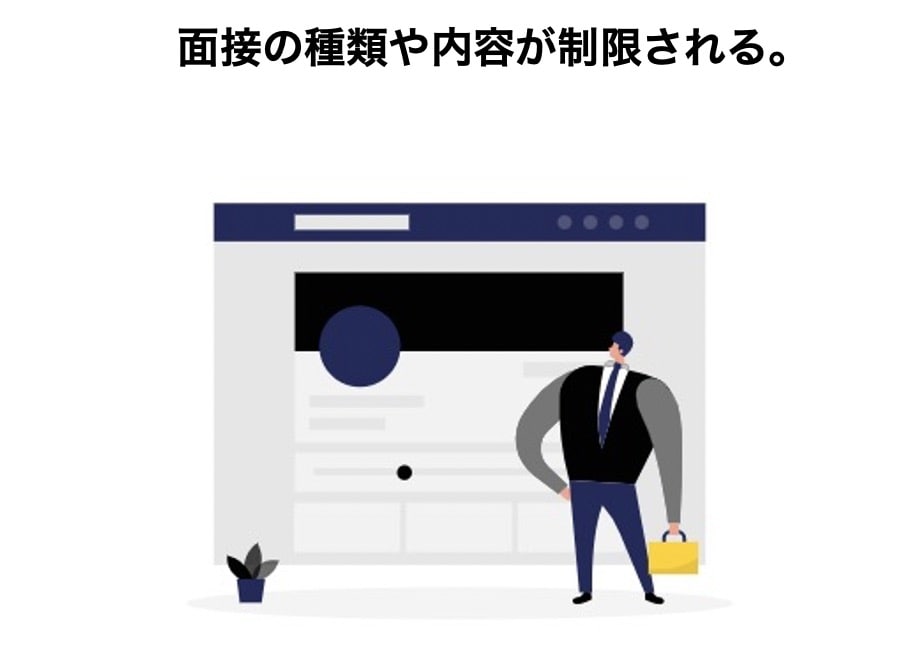
集団面接やグループディスカッション等の複数の人間の参加が必要となる場合に、ネット環境との関係で会話にラグが発生するといったことからオンライン面接には向いていないとして実施を取りやめる企業も実は多くなっています。
集団面接やグループディスカッションを取り入れている企業は他者とのコミュニケーションの採り方をみたい、そのような能力がある者に入社して欲しいと考えている企業にとってはオンライン面接はあまりマッチしていません。
このように面接の種類や内容が限定されてしまうと企業にとって欲しいと思える人材かどうかを検討することが困難となってしましうという事態が発生してしまいます。
どのような企業がオンライン面接を存続させるべきか
オンライン面接のメリットとデメリットをみてきました。
ではどのような企業がオンライン面接を存続させていくべきなのでしょうか。
ここでは求人への応募数に左右される「人気企業」と「不人気企業」の2パターンに分けて解説します。
人気企業の場合
オンライン面接を継続する
人気の企業の面接を受けたいと考える就活生はすでに就職したいという願望が強く企業側から強く働きかける必要はありません。
また、受けたいと考える就活生が地方や都市部などさまざまな地域にいるということが想定されます。
したがって、広く浅く対応することが可能となるオンライン面接をメインに導入することでより多くの人材に出会うチャンスを作ることが大切なように思います。
また、企業にとって特に来て欲しいと思う人材について対面で実施することで信頼関係をより深く構築することで選んでもらえるようするということが可能となります。
不人気企業の場合
対面の面接に切り替えていく
不人気企業の場合、就活生には第2希望や第3希望で就職したいという考える者が多く、人気企業に比べると就職したいという願望はどうしても弱くなってしまいます。
また、全国的に面接を受けたいと考える就活生が広く分布しているということも考えにくいでしょう。
このような場合には企業としては就活生側に強く働きかける必要があるといえます。
間口は狭くなってしまいますが就活生との信頼関係を深く構築するために対面での面接を行っていく必要があるといえます。
4:まとめ
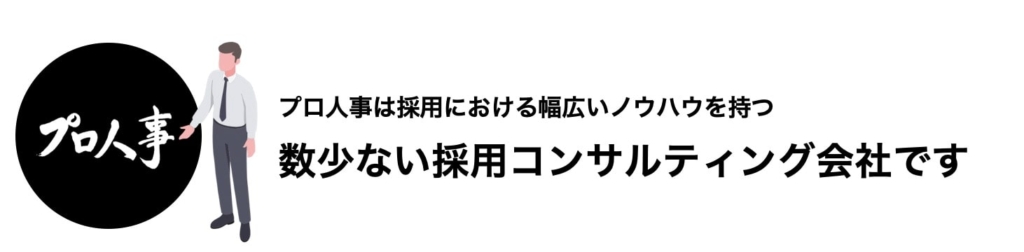
今回は人事部にとって身近にある「新しい生活様式」の一つであるオンライン面接にしぼってアフターコロナにおいても存続させるべきかを解説していきました。
オンライン面接に限らず「新しい生活様式」の一環として企業でも急遽取り入れたといた制度や変更せざるを得なかった体制等がたくさんあると思います。
導入して良かったというものから、やはり合っていないのではないかというものまで様々なものがあると思いますがコロナが落ち着きを見せたいま見直しが必要になってきたのではないでしょうか。
人事に特化したプロ人事だからこそアフターコロナにおける人事部の新しい生活様式を提案することができます。
また、こちらの記事ではオンライン面接のノウハウについて解説しておりますので、オンライン面接の実施についてお悩みの方はあわせてご覧ください。