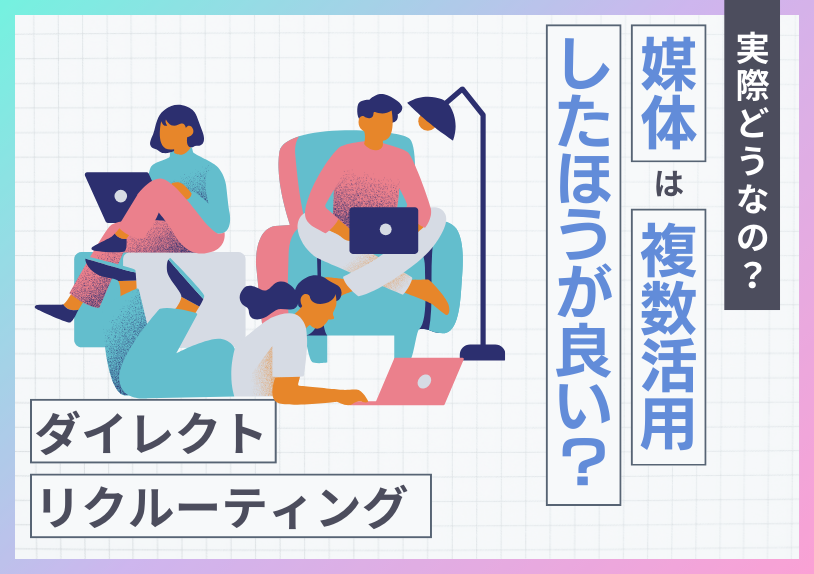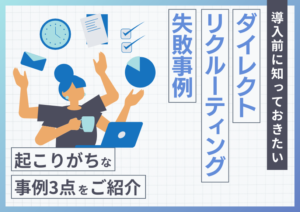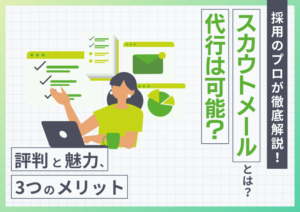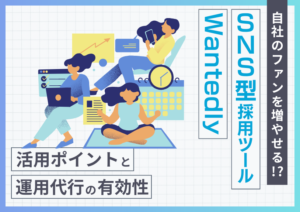ダイレクトリクルーティング媒体は複数活用すべき?ダイレクトリクルーティングの運用代行会社が解説
攻めの採用手法として注目を集める【ダイレクトリクルーティング】。
人材獲得競争が難化しているなかで、企業から積極的に動くことで、希望人材の獲得を目指すことができる採用手法であることから、導入する企業が増加しております。
昨今では導入企業の増加に伴い、様々な特徴をもつダイレクトリクルーティング媒体が展開されるようになりました。
このように勢いのある採用手法ではありますが、自社にマッチする媒体とはなにか、そもそも媒体は複数活用した方が効率的なのかと、ダイレクトリクルーティングの媒体にお悩みになった方も一定数いらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、ダイレクトリクルーティングの導入は複数の媒体を活用すべきなのか、プロの人事が詳しく解説します!

ダイレクトリクルーティングで
採用の質を上げてみませんか?
採用に特化したプロ人事だからこそ、より効果的なダイレクトリクルーティングの運用を
ご提案することができます!
ダイレクトリクルーティングに関する業務内容も幅広く対応しておりますので
ぜひお気軽にお問い合わせください!
ダイレクトリクルーティングとは?
ダイレクトリクルーティングは、企業から直接欲しい人材にアプローチすることができる採用手法が特徴です。
少子化に伴う働き手の不足に伴い採用市場も縮小化し、売り手市場が継続していることから人材獲得競争が難化の一途を辿っています。
とりわけ、IT・エンジニアなどの専門職はこの傾向が顕著に出ています。
従来の採用手法のように企業が待っていては、なかなか採用目標を達成することが状況です。
そこで、企業から求職者に対して”攻め”の姿勢をとることができるダイレクトリクルーティングが注目を浴びるようになりました。
ダイレトリクルーティングを活用する媒体の紹介
では、ダイレクトリクルーティングを導入するにあたり、まずどのような媒体を選定すべきでしょうか。
導入初期はお悩みになる企業も多いかと考えます。
この章では、どのような媒体があるのか簡潔に紹介します。
新卒採用
- OfferBox(運営会社:株式会社i-plug)
-
新卒採用のオファー型サービスとしてNO.1と呼ばれており、学生からもっとも認知されている媒体となります。2025年1月時点では登録者数は213,000名にも上り(※)、就活生のおよそ3人に1人が利用している計算になります。
- LabBase(運営会社:株式会社POL)
-
理系学生の採用に特化したダイレクトリクルーティング媒体です。
MARCH, 国公立大学に所属する理系学生の登録割合が80%を超えており、独自の研究室データを保有していることから(※)、他の求人サイトを利用していない理系学生にもアプローチをすることができます。※ 引用:【企業向け】理系採用ならLabBase
中途採用
- ビズリーチ(運営:株式会社ビズリーチ)
-
ハイクラス転職サイトとして認知されており、登録する場合に年収に関する条件が定められています。
年収に条件が定められていることもあって、年齢層は比較的高めになっています。
ただし、最近では20代~30代に登録者も増えており、若手な優秀層も揃いつつあります。 - Eight Cereer Design(運営:株式会社Sansan)
-
同会社が運営する名刺交換アプリ【Eight】と連携しており、名刺交換アプリを利用しているユーザーに対してアプローチをすることがでできるのが特徴です。
潜在的転職者層のへのアプローチを可能としているダイレクトリクルーティング媒体となっています。
新卒・中途採用
- Wantedly(運営:ウォンテッドリー株式会社)
-
企業の魅力を候補者にアピールし共感をしてもらうことをコンセプトとしているダイレクトリクルーティング媒体です。
20代~30代の若手層が多く、採用難易度の高いエンジニア等のIT関連の業種の者が利用しています。
ダイレクトリクルーティング媒体は基本的に新卒また中途の採用に特化したもの、もしくはその両方を対象とするかで大きく分かれます。
さらに、新卒採用であれば理系学生に特化したもの、中途採用でもエンジニアに強いものであったりと、対象となるターゲットや業種が細分化されるのが特徴です。
中途採用の中には、潜在的転職者へとアプローチすることができるものもあります。
潜在的転職者とは、「転職サイトに登録しておらず、積極的に転職活動を行っていなかったり、そもそも転職意欲がない者」のことを指します。
ダイレクトリクルーティングについてよくある質問
- 転職サイトに登録してない者に対してアプローチをかけることができるのか?
-
転職機能をメインとしていない(ビジネスSNS・名刺アプリ)ものであれば、転職活動をする気がない潜在的転職者も利用をする可能性が高く、このユーザーに対して企業からアプローチをすることが可能となっているため、潜在的転職者の採用が可能です。
潜在的転職者は従来の採用手法ではアプローチすることができていない新たな採用市場と言えます。
上述したように、採用市場自体も縮小し、採用競合する他社との競争が激化している要因であるからこそ、新たな採用市場を開拓することができる点はダイレクトリクルーティング媒体のメリットともいえるでしょう。
このように、ダイレクトリクルーティング媒体には様々なものがありますが、基本的には自社が採用したい人材のゾーンとマッチするものかどうかが選定のポイントです。
例えば、新卒かつ理系学生を採用したい場合、まずは新卒採用の大手であるOfferboxが候補として挙げられ、理系学生の採用に特化したLabBaseもマッチする媒体と分析できるでしょう。
このように、媒体は基本的に広い業種や学部を網羅的に集めている媒体と特化型のものに大きく分けられることになりますが、特定の職種やスキルをもつものの採用をするのであれば特化型の媒体を一つ利用すればよいのではないかと思われるかもしれません。
この点について、複数媒体を利用すべきか否かについて次の章で解説いたします。
ダイレクトリクルーティング媒体は複数活用した方が良い?
先に結論を述べると、採用に力を入れるのであれば複数活用をすることをオススメします。
プロ人事が複数利用をオススメしている理由は大きく2つです。
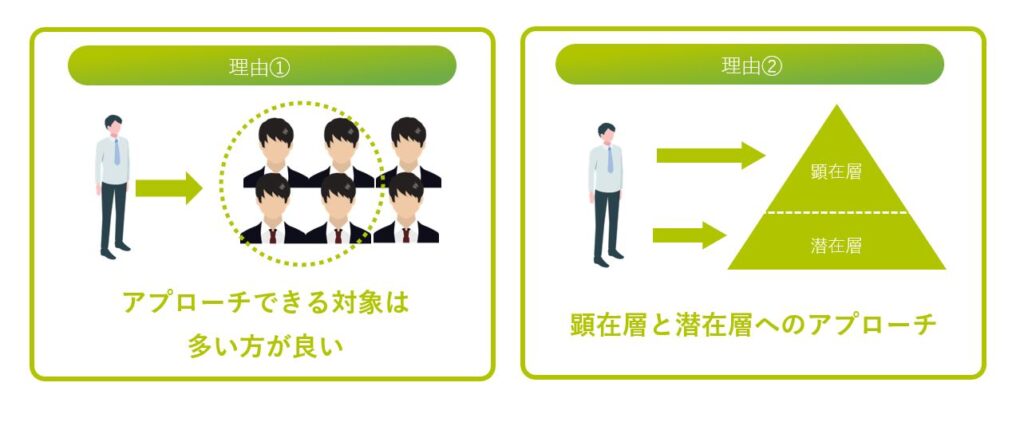
理由①:アプローチできる対象は多い方が良い
ダイレクトリクルーティングは候補者に対してスカウトメールを作成・送信することでアプローチをかけていきますが、送った相手が必ずしも返信をしてきたり、返信があったからといって内定承諾にまで至るということはありません。
特に人気人材となってくると複数の企業からスカウトメールが送られているため、競争率も高く、なかなか採用難易度も高くなってきます。
大体、300通送信して1人採用が目安となっているため、送信するスカウトメールの数はもちろんのことより多くの候補者に対してアプローチをかける必要があります。
そのため、複数の媒体を利用することで、アプローチできる対象をなるべく増やす必要があるのです。
理由②:潜在的転職者にもアプローチをする必要がある
優秀な人材やエンジニアやコンサルティングなどの専門職系となってくると、積極的に転職を望んでいる顕在的転職者だけでは、なかなか数が集まりません。
また、人材の数が少ないのに対して、企業側の需要が高いとなると、当然競争率は跳ね上がることになるでしょう。
このような場合には、現時点では積極的に転職活動を行なっていない潜在的転職者へのアプローチもしていくことで人材を集めていきます。
ただし、潜在的転職者は、転職活動を積極的に行う必要がないほど、今の会社にある程度満足しているため、顕在的転職者と比較すると採用難易度は高くなります。
今の会社に大きな不満がないのは、職場でも充分に活躍していたり労働条件も良いことが多いです。
言い換えると、潜在的転職者は優秀な人材が揃っている証拠にもなります。
顕在的転職者と潜在的転職者では、採用市場が重複せず、優秀な人材の採用も可能になります。
そのため、顕在的転職者を対象とする媒体と潜在的転職者にアプローチすることができる媒体の複数活用もオススメしております。
複数のダイレクトリクルーティング媒体を活用する際の注意点
本格的にダイレクトリクルーティングを運用し採用を成功させたい場合は、できる限り複数媒体を利用することをオススメしています。
とはいえ、ダイレクトリクルーティングは能動的に企業が動くことになるからこそ、従来の採用活動と比較すると工数や時間が増加し、人事部へかかる負担も大きくなっています。
そのため複数媒体の運用に耐えうるだけのマンパワーがないという企業も少なくありません。
このような企業にオススメしているのが、スカウト代行サービス(ダイレクトリクルーティングの運用代行サービス)です。
次の章では、プロ人事のスカウト代行サービスについてご紹介いたします。
プロ人事が展開しているスカウト代行サービス
プロ人事が展開しているスカウト代行サービスでは、ダイレクトリクルーティングの運用を外部に委託することになるため、人事部にかかる運用の負担を緩和することができます。
ですので、マンパワーに自信がない企業様にとってオススメできるサービスであることはもちろんのこと、他にも様々なメリットがあります。
プロ人事のスカウト代行サービスのメリットを3つをご紹介します!
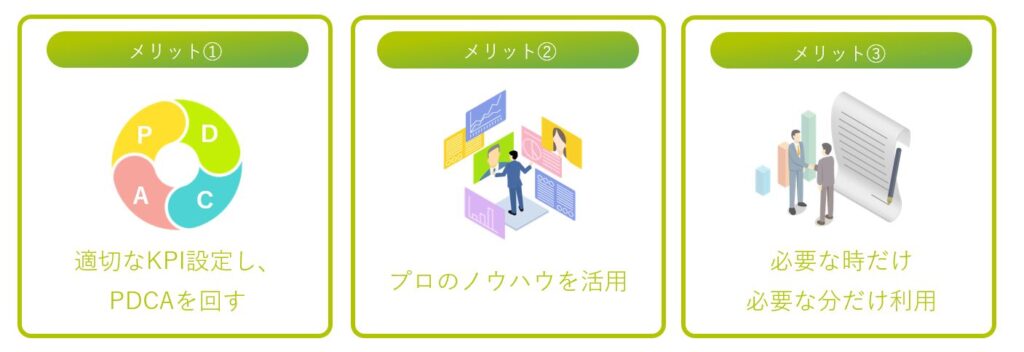
①適切なKPI設定とPDCAサイクルを回せる
ダイレクトリクルーティングでは、スカウトメールの作成自体に注目されがちですが、運用を成功させるには、PDCAサイクルを適切に回していくことで、効率的な運用を実現させていく必要があります。
PDCAサイクルをまわす上で重要なのが、適切なKPIの設定です。
しかしこれを自社のみで行うには、詳細なデータの分析とノウハウが必要となることから一筋縄ではいかないでしょう。
ダイレクトリクルーティングの返信率のデータ分析で例えると、返信率が高い=欲しい人材が獲得できているとは限りません。
若手の優秀層など、人気の人材の獲得を目標としている場合は、企業間が採用しようと競争率が高くなります。複数の企業から大量にスカウトメッセージが来るため、必然的に返信率の平均も低くなります。
一方で、あまり競争率が高くない(比較的年齢層、就職氷河期の世代など)は返信率が高くなるためです。
ですので、採用対象とする人材の平均返信率に対して、数値が高くなっている場合は注意が必要です。
その場合は、本当に欲しい人材からの返信が来ているのかという実態まで見ていく必要があります。
とはいえ、職種や年齢などの層の返信率の相場まで把握している企業はほとんどありませんし、データ収集も難易度が高いです。
採用代行を専門に扱っているプロ人事であれば、自社だけでは取得することができないデータも収集しております。
そのデータとノウハウをもとに、より正確にKPIを設定しPDCAサイクルを回すことをお手伝いいたします。
メリット②:プロのノウハウと知見を得られる
トライアンドエラーをくり返すことでノウハウ構築はできますが、時間がかかる上に、構築されるまでの間に他の企業に欲しい人材を獲得されてしまいます。
ダイレクトリクルーティングのノウハウを有するプロ人事を活用することで、ノウハウ構築までの時間や負担なく、導入当初から全力で候補者にアプローチをすることが可能となります。
またダイレクトリクルーティングを導入する企業も増加していることから採用競合する他社の数も多くなっているからこそ、独自の強みを出して差別化をしていくのかが重要になります。
プロのノウハウを活用できるスカウト代行サービスを利用すること自体が他の企業との差別化を図ることができると言えるでしょう。
メリット③:必要な時に必要な分だけ利用できる
人事部のマンパワーの解決に関しては代行会社を活用する以外に、正社員や派遣社員を採用することで増員をするということも考えられます。
しかし、正社員を採用する場合はダイレクトリクルーティングの運用を停止した場合の対応がネックとなるでしょう。
ダイレクトリクルーティングが基本的に通年を通して運用をするのではなく、採用に力を入れている期間は集中的に運用し、採用期間が経過した後は一時的に運用を停止(中断)することになります。
人事部のマンパワーが不足する期間は変動的なものになるため、正社員として人員を増員した場合、停止中は浮くことになりますが、正社員は簡単に辞めてもらうことができませんので、その分のコストがかかることになります。
派遣社員を採用する場合は正社員と比較すると停止期間中の対応がしやすいものの、ノウハウが属人的になるため、運用を再開する時に、ノウハウをもった派遣社員を採用できるかの保証はありません。
ノウハウがない場合は最初から構築していくという点では、再度時間とコストがかかることになるでしょう。
プロ人事のスカウト代行を導入すると、運用を停止(中断)する際と同時に代行サービスの方も停止(中断)をしていただくことが可能です。
変動するマンパワーの問題に柔軟に対応できることに加えて、プロ人事の担当者は弊社に所属して日々ノウハウを構築していることから、スムーズに運用を再開できるのも魅力です!
まとめ
今回はダイレクトリクルーティング媒体の複数活用について解説をしてまいりました。
どうしても1つの媒体だけの運用ですと、そのなかでも自社が欲しい人材の数に限りがでてくるため、なるべく採用市場が重複しない媒体を複数利用することでアプローチをかけることができる候補者の数を増やす必要があります。
とはいえ、人事部のマンパワー的に複数媒体の運用が厳しい企業も少なくはありませんし、一つの媒体を運用ですらいっぱいいっぱいという企業もあるかと思います。
プロ人事では【スカウト代行サービス】も展開しているため、サービスの導入をご検討の方はぜひお問い合わせいただけると嬉しいです!